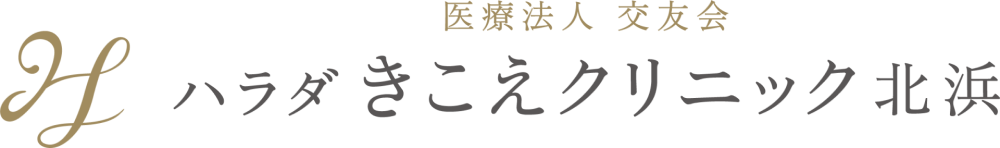- 補聴器をなぜ診療所が扱うのか
-
補聴器って、眼鏡店で売ってるじゃないか。どうして診療所で扱うのだろうと考える方が多いのではないでしょうか。もともと補聴器は雑品として日本に入ってきました。当然そのころは一種の電気製品であり医療装具という認識はありませんでした。ところがその後聴覚医学が進歩し補聴器が役に立つにはどうすればいいのかが世界中で数多く研究されてきました。そこでわかったことは、かなりきめ細かな調整と聴覚リハビリテーションを行わなければ補聴器が役立つ確率は極めて低いということです。つまり補聴器は医療装具として医療機関が扱うべき物だったのです。買ってハイ終わりでないのです。しかし、補聴器診療を本気で取り組んでいる医療機関は数えるほどしかありません。
- 買う前に行われるべきこと
-
例えば車を買う前に皆さんは何をなさいますか? 試乗ですか? 資料請求ですか? スペックの研究? 違います。あまりにも当たり前すぎてぱっと思いつかないかもしれませんね。お抱え運転手を雇える人以外は当然免許取得ですね。運転スキルや交通法規を知らずして車の運転なんてとても危険な行為です。座学で勉強したり教習車で運転スキルを磨いたりする必要があります。
補聴器には免許などありませんが、聞くスキルがなければ役に立ちません。そのスキルを磨くには、補聴器を装用して長時間音声を聞く必要があります。 - 補聴器を活用するのは実は大変
-
では補聴器を装用して聴覚を刺激し続ければうまくいくのかというとそうではありません。聴力の形にピタッとはまった調整が伴わないとうまくいきません。それには、技術を伴った調整を繰り返す必要があります。医療とは医療者と患者の共同作業がうまくかみ合わないと成立しません。補聴器も全く医療の原則にあてはまります。まずは何を買うかよりどこから買うかが大切です。この業界は玉石混交です。慎重に選ぶ必要があります。医療機関の中にあるからと言っても単に販売店の出張所のところもあります。すべてが悪いわけではありませんが、慎重に選ぶ必要があります。院長に質問した場合いつも的確な答えが返ってくればかなり信頼できると思います。
- 当院での診療
-
当院では、精密な調整はもちろんのこと聴覚リハビリテーションが進むように長時間装用をしていただいています。また試聴期間は無料で最長3か月はできるようにしています。試聴期間中に使えそうもなければ中止することも可能です。試聴していただいた患者さんの85%は効果が見られ購入に至ります。
- 購入に至らないケース
-
それでも補聴器の適応はあり試聴を開始した方の15%程度は購入に至らないのですが、客観的に効果が見られないケースは意外と少なく半分以下です。違和感や周囲の騒音がうるさい、自分の声が響く、咀嚼音が大きい、イメージと違う、頭痛がするなど補聴効果以外の理由が意外に多いのです。また騒がしい居酒屋などの過酷な条件下での効果が不十分でやめる方もおられます。慣れてしまえば解決することも多いのですが、その間モチベーションが無いと耐えられないようです。モチベーションは「聞こえるようにしたい」というニーズがなければ生じません。ニーズは、仕事やコミュニティをお持ちでないとなかなか生まれないものです。
それともう一つうまくいかない大きな原因は、「補聴器を装用すると元の聞こえにならなければならない。」という間違った信念です。高価な補聴器を買うのだから元通りに戻ってほしいと考えるのが人情ですが実際にはありえません。ほとんどの難聴である感音難聴は「補充現象・周波数弁別能低下・時間分解能低下」など語音弁別を悪化させる現象があり、外耳道内に異物を挿入するという不自然な行為による音響特性の変化などの理由により補聴器で決して元通りにはなりません。メガネはかけるとよく見えるとよく比較されますが、そもそもメガネは屈折異常を矯正するものであり視覚障害に対する装具ではありません。お互い似て非なるものであり比較するのは適切ではありません。両者の根本的な違いを動画で解説しておりますのでご覧ください。補聴器はなぜメガネのように簡単にいかないのかを解説したYouTube動画です。