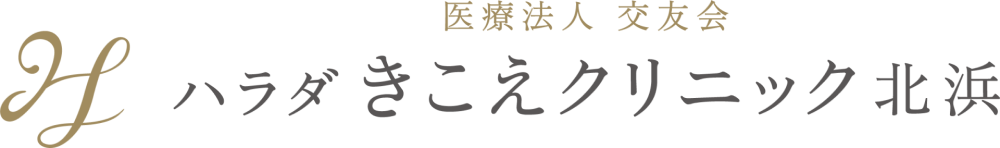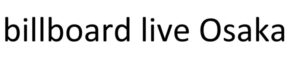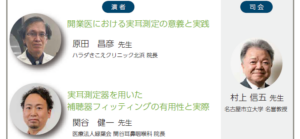2025年10月16・17日に成田国際文化会館で第70回日本聴覚医学会総会・学術講演会が開催されました。聴覚分野の様々な演題が発表される年に一度の催しです。私は当然専門分野である補聴器関係の発表を聴講してまいりました。その一部を紹介したいと思います。
演題番号:演題と表示します。演者と所属医療機関は省略します。
66 90代以上の高齢者に対する補聴器適合の試み
90歳以上の高齢者82例(男36例、女46例)に対し3か月をめどに補聴器を貸し出しその動向を調査。補聴器装用の動機は、本人希望62% 家族の希望26% 医師の勧め9% その他3%です。補聴器購入率は、94% 3例装用拒否 2例死亡。言葉の聞き取り検査では、補聴器非装用時60±23%、装用時69±19%で補聴器が適合した確率が100(ちょっと高すぎるような)。結論が90歳以上でも補聴器活用は可能である。
67 高齢者に対する補聴前後の認知機能
長谷川式寛一の評価スケール(HDS-R)により補聴器装用が認知機能低下を抑制するかを見る。補聴器を8時間以上装用させて補聴器装用群と非装用群の差を見た。(装用期間があいまい)
装用群64例中13例の20.3% 非装用群35例中14例40.0%が進行した。装用群の方が進行率が少なく、補聴器装用が認知症の進行抑制があることを示唆。
68 補聴器助成制度導入・非導入地域間での初回補聴器購入高齢者の特性の比較
助成金があるからと言って補聴器導入の年齢や聴力、補聴器外来初診時の本人の関心度の有意差は認めなかった。両耳装用率は、非導入地域の方が優位に高かった。(お金をもらった方が両側を購入しないという不思議な現象)
目次
成田駅前からくり時計
78 高音急墜型感音難聴患者における臨床像および聴覚補償の検討
低音しか聞こえない我々を悩ませる聴力の症例に対する検討。
高音急墜型感音難聴症例男性3例女性23例、20歳から72歳中央値43歳の検討。
難聴自覚が11~30歳:43%、31~50歳:34%と多くそれより若年と高齢は少数。
遺伝学的検査は18例に施行、9例に遺伝子が見つかる。補聴器装用は17例、開始年齢は18~70歳(中央値52歳) 人工内耳装用が11例、補聴器開始から人工内耳手術まで0~12年、7例が10年以内に人工内耳に移行。早期に人工内耳を検討することが有益。
(やはり最後は人工内耳です。)
183 医療者主導の補聴器診療を目指す言語聴覚士を対象とした遠隔育成事業
対象は補聴器診療に携わるSTとSTと協働する耳鼻咽喉科医である。医療機関に協力要請を行い、座学、実務経験のあるSTによる補聴器調整指導、現地実習による実践的学びである。今のところ試行段階である。(補聴器外来の絶対数の不足は、人材確保のむつかしさが原因の一つとなっています。)
185 持参補聴器外来での補聴器導入経緯別の形態と装用効果についての検討
80例を対象、病院から16例(両側12例)、認定店から10例(4例)、非認定店から54例(38例)非認定店が多いが器種変更は施設間の大差はない。保証期間中の持ち込みは販売店には連絡している。(非認定店では買わない方がよさそう)
186 当院補聴器外来で相応訓練を行った難聴患者の臨床像
2016年4月から8年間549例。平均聴力(4分法)と最高語音明瞭度
| 年齢 | 聴力 | 明瞭度 |
| <65 | 50.1dB | 73.8% |
| >=65 <75 | 49.0dB | 71.5% |
| >=75 <85 | 51.1dB | 65.8% |
| >=85 | 55.1dB | 56.7% |
購入率95.9% 適合率98.4% 持参した患者は35%
(年齢による聴力差は小さいわりに高齢者の語音明瞭度の低下は著明ですね。)
演題は適当に抜粋して掲載しました。以上です。